こんにちはnikokoです。
毎日の家事。次から次へとやることが出てきて、「いつになったら終わるの~!?」とため息をつきたくなることはありませんか?
しかも、とてつもなく忙しい時や時間があまりない時にかぎって
「ぼく(わたし)もいっしょにご飯を作りたい!!」
「一人でお掃除してあげるね!!」
など、大人と一緒に何かをしたい・作りたいと子供たちからのお手伝いの要望があったりします。
「え!?今?」と、時間との戦いの時は、つい言いたくなる場合も・・・。
「いっしょにしたい!!」「お手伝いがしたい!」とその言葉が本当はうれしいはずなのにタイミングがあわないと、ギョ!!と困ってしまう時も正直、わたしはありました(笑)
今日は、大人と一緒に「何かやってみたい・作ってみたい!!」とお手伝いの意欲が出てきた子供たちと一緒に、なるべく少しでも楽しく家事を進めていけるように、私なりに工夫してみたことをまとめてみました。
今回は、お料理編です。
・朝のバタバタした時間、夕飯作りのあわただしい時に、もし子供たちから「一緒につくりたいな~!!」という声が聞こえてきたら・・・。
・こんな忙しい時に、ちょっとでも手伝ってもらえたら本当はうれしいけど、かえってちらかってしまい洗い物が増えるたり時間がかかるから、なかなか「お手伝い」を促す勇気がでない・・・。
・反対に手伝ってほしい時に手伝ってくれない・・・。
などなど、お料理の「お手伝い」について書いていきたいと思います。
「お手伝い」の大切さ
一言で「お手伝い」と言いますが、その中身は奥深いものがあるのではないかと私は考えています。
「お手伝い」をしてもらう方は、そのやり方を「お手伝い」をする方に教えることもでき、
かつ、自分の手助けをしてもらうことも可能です。
反対に「お手伝い」をする方は、そのやり方を「お手伝い」を通じて身に着けることができ、かつ、人の役にたてた達成感を味わえたり、「~してあげたい!!」という人を思いやる心も培うことができると考えます。
大きくいえば、「お手伝い」をしてもらうことにより、手伝ってくれる人が手伝ってもらう人にとって必要であるという存在を示すものなのかもしれません。それは、反対に手伝ってもらう人が手伝ってくれる人にとっても同じことが言えるのでしょう。
そして、「お手伝い」をしてくれたあとの子供たちの表情は、どこか満足気です。
「ぼく(わたし)、できた!!」と誇らしげな感じも見受けられました。
そして何より、手伝ってもらう側の「ありがとう!!」という言葉がとても嬉しそうでした。
「ありがとう!助かったよ!」
その一言で、少し失敗してしまった時でも、「お手伝い」ができたという満足感は伝わってきたように思います。
お互いに感謝のココロも再認識できる良い機会になるのではないでしょうか。
時間に余裕があるときの「お手伝い」
「ぼくも(わたしも)作りたい!!」と手を洗って、さっそうとキッチンに来る子供たち。
手伝ってもらう側に時間の余裕がある場合は、丁寧に作り方を子供たちに教えてあげると、次回のお手伝いからは、得意げに作ってくれたり、何回か頼むうちに本当に助かることも増えていきました。
ただ、最初は子供たちにとって初めて作るものも多いので、時間はかかります。
材料を散らかしてしまう場合もありますが、そこはちょっと目をつぶっていきます。できる限りでいいのでなるべくギュッと(笑)
~我が家のおおまかなお手伝い内容~
<未就学児のころのお手伝い>
手伝いの途中、味見をしたくなるのか、食べ物を口に入れやすいので、火の通ったものを頼んでいました。
また、混ぜるだけという簡単な作業もお願いしていました。
例・コロッケを作る際に、火の通ったひき肉やじゃがいもをまるめていく作業。
・サラダの盛り付け
・卵やドレッシングやホットケーキ、生クリームなど混ぜていく作業。
<小学1~4学年のころのお手伝い>
いくつかの作る過程を楽しみ始めたので、できそうなことは頼んでみたり、挑戦させたりしました。
例・揚げ物の小麦粉・卵・パン粉をつけていく作業
・お味噌汁の味付け
・お米とぎ
<小学高学年~>
・材料を切る。
・料理作りで材料を焼く作調理。
・いろんな味付け
私は、だいたい上記のような感じで進めていきました。
どの段階でも楽しく作業していくことを心がけました。
例えば、揚げ物の小麦粉・卵・パン粉をつけていく調理では
小麦粉・・・砂場
卵・・・おふろ
パン粉・・・布団 として、
「コロッケさんが砂場で遊んでるね。ほら、卵のお風呂に入って。パン粉のお布団で寝るから、きちんとパン粉のお布団かけてあげてね。」
と順番が分かりやすいように見立てながら一緒に作る場合もありました。
子供たちは、すぐにイメージできたのか、すんなりと調理していたように思います。
みんなで楽しく料理が作れたら、きっと料理もおいしくなりますよね。
時間に余裕がない時の「お手伝い」
とても急いでいる時、忙しくてバタバタの時、やることがありすぎる時・・・そんな時にかぎって
「ぼく(わたし)もする~!!」と言われたことはありませんか?
「あとでね。」
「今度ね。」
と、ついつい言ってしまう時も多々ありました。
残念そうにキッチンから離れていく姿を見ると、やっぱり「お手伝い」をさせてあげたくもなりましたが、なんせ時間がない!自分で作ってしまった方が、手っ取り早い・・・。
そう思って、やはり自分でパパッと作ってしまうことが多かったです。
そんな時、心掛けていたのが、
「ありがとうね。」
という言葉です。
手伝おうとしてくれたその気持ちを大事にしたくて、必ず感謝の気持ちを伝えるようにしていました。
私の気のせいかもしれませんが、感謝を伝えた後は、少し子供たちの表情も明るくなっていたように見えました。
また、最初から全てお手伝いしてもらうのではなく、一部を頼んだりするという方法もとったりしていました。
盛り付けだけとか本当に簡単な「お手伝い」をしてもらい、時間がかかりそうなところは自分でして、手のかからない調理だけ手伝ってもらうこともありました。
お料理の「お手伝い」で好き嫌いが克服?!
子供たちの嫌いな食べ物・苦手な食べ物がある料理の時、その料理を一緒に作ったりすると、食べてくれるということがありました。
「これ、ぼく(わたし)が作ったんだよ!!」と、ちょっと自慢気な様子だったからか、自分で作った料理だから愛着があるのか、理由はよく分かりませんが、苦手な食材も食べてくれる頻度は多かったように思います。
作ることの楽しさだけでなく、手間がかかる大変さも感じたりすると、もしかしたら、箸もすすむのかもしれませんね。
まとめ
あくまでも、私の体験談であって、「お手伝い」は、その子その子にあったペースでいいと思います。
そして、包丁などを使う場合は、使い方もきちんと教え、怪我をしないように気を付けることも大事かなと思います。
どの段階でも、最初は慣れないし時間もかかります。
調理器具によっては、怪我につながる場合もあるので、使い方も教えてあげなければいけません。
ご飯は作らないといけないし、あれこれ注意して見ていけなければいけないしで、大変な時も出でくると思います。
「お手伝い」をさせたいけど、自分にゆとりがなく、イライラしてしまっては、せっかくのご飯作りも楽しくできないので、そんな時は、みんなで無理はしなくてもいいのかなと思いました。
無理にやらせても、きっと楽しくないと思うし、子供たちの「お手伝い」が楽しい!助けてあげたい!という気持ちを最優先に考えてあげるとうまくいくのかもしれません。
そして、「お手伝い」を通じて、互いに感謝のココロをもつ大切さも大事にしていけたらと思いました。
最後まで読んでいただき、ありがとうございました。



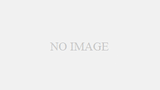
コメント