![]() こんにちは、nikokoです。
こんにちは、nikokoです。
こどもたちが幼稚園・保育園に入園したり、小学校に入学し、生活に慣れてくる頃、ピアノを子供に習わせたい!とお考えのご家族の方も多いのではないでしょうか。
ピアノなどの楽器は、右手・左手が別々の動作になり、なかなか最初から両手でうまく弾くことは難しいです。
子供自身が「ピアノを習ってみたい!」と意欲満々で始めても、壁にぶつかることは多々でてくるし、時には、練習がうまくいかず子供が泣いてしまうこともあるかと思います。
また、ピアノは基本毎日練習することがベストだとは思うのですが、なかなか毎日ピアノの練習を続けるというのは大変の時もあります。
ただ、弾けるとカッコイイ!!そして、何より本当に楽しいです!
スラスラ弾ける日を目指して、練習を頑張れば、ちゃんと弾けるようになっていくのもピアノです。
幼いころはたくさん遊びたいですし、最近の忙しい学校生活の後に+プラスしてレッスンや練習をするとなると、時にはハードだなと考えてします所も正直あります。
私自身、幼いころにピアノを習っていた経験(私の場合、5歳~13歳まででした)があるのですが、確かにピアノを習っていて、「楽しい!!」という記憶ばかりではありませんでした。
うまく弾けずに泣いていたり、結構、昔のピアノの先生はとても厳しかったりした(わたしの思い込みかもしれませんが・・・)ので、怒られて悲しかった記憶も残っています。
しかし、8年間続けられたのは、先ほども述べたように、弾けた時のうれしさと単純にピアノを弾くことが好きだったからだと思います。
今回は、自分の子供時代、そして、我が家の子供がピアノの練習をしていた時を思いだしながら、なるべく苦にならないピアノの練習方法についてまとめてみようと思います。
ピアノの仕組みを知ろう!
ピアノを習い始める時に、まず、ピアノの音がなぜ鳴るのか、ピアノはどんな楽器の種類なのか等、ピアノの仕組みを知ると、よりピアノという楽器に対して愛着や親しみが持てるかもしれません。
もしおうちにピアノがあれば、調律師の方が来た時に一緒に調律の仕方を見せてもらうと仕組みが分かってきます。
電子ピアノの方はレッスンの先生に頼めば、ピアノの中身を見せてくれてり、先生の中には仕組みの説明をしてくれる場合があります。
確か、うさぎのような形をしたものが弦をたたいて音が出ていたような・・・。
ピアノは鍵盤楽器といわれたりしますが、実際子供のレッスンの先生がその弦だけをはじいて音を出すとまるでハープのような本当に本当に綺麗な音色でした。
まるでピアノは弦楽器の仲間のようにも思えました。
そして、ピアノは木でできている部分が多いです。
鍵盤は上側から見ると白と黒に見えますが、横側からみると見た目も感触も「木」の温かみも感じることができます。
私は自分の子供にもよくこんなことを言ったりしていました。
「ピアノは木でできている。木は湿度によってのびたり縮んだりして生きている。
だから、気持ちを込めて弾けばきれいな音がでるけど、イライラしたりしている雑な音になったりする。気持ちがそのまま音になったりする時がある。」
と。
楽しくレッスンできたら・・「音楽」という字の通り、音を楽しんで弾くことができたら、
とても嬉しいですね。
もちろん、ピアノの仕組みを知ることは、習い始める時だけでなく、途中になっても構いません。
仕組みを知ると楽器を大切に扱うココロも育まれると私は考えます。
練習を毎日続けるコツ
ピアノを上手に両手でスラスラと弾きたい!!
ほとんどの子供がそう思うと思います。
ただ、みんなが最初からうまく弾けるわけではありません。
プロのピアニストが大きな舞台でスラスラかっこよく弾く姿の裏には、たくさんの練習や努力の積み重ねがあるでしょう。
もちろん、天才的な才能を持った人もいるかと思いますが、練習はみんながしていることだと思います。
「練習すれば、うまくなれる!」そう思っても、「毎日レッスン・練習を続ける」ということは、幼い子供たちにとって、大変だと感じる子も多いと思います。
最近の学校生活は、本当にイベントも多く、日本の子供たちは忙しいなと思う面もあります。
学校・宿題・ピアノ以外の習い事・そしてピアノの練習・・・いやいや、遊ぶ時間も必要!
となると、1日が本当に目まぐるしくなっちゃいますよね。
でも、ピアノは毎日練習することが上達への基本です。
どうしたらいいの~!!と叫びたくなりますが、私の場合ルーティンを最初から決めて習いました。
学校(昔は土曜も学校だったせいかわりと早く終わっていたような・・)➡宿題➡ピアノ➡遊び
と最初から習慣づけていると、なんとなくピアノを毎日触らないとスッキリしないような気がして、自然と練習していました。
わが子の場合、まだ、ピアノを習い始めた時期が就学児前だったため最初にこんな話をしました。
「あなたも毎日ご飯を食べるでしょ。ピアノさんのご飯はあなたの練習なんだよ。だから毎日練習してピアノさんにご飯をあげてね。」
なんとなく、毎日の練習が大事なことだと話をしました。
自分の習慣の中の一部に「ピアノの練習」が入ると、苦にならずレッスン・練習に結びつくでしょう。
また、習慣づけが難しい場合には、「うまくなりたい!」という気持ちを大切にしていってあげるとレッスン・練習につながっていくかもしれません。
レッスン・練習の先にスラスラ弾く自分の姿があることを子供自身が知り、実際に感じることができると、それが楽しみにもなります。
そして、できることなら、嫌々練習するのではなく、楽しく練習できるように何かレッスン・練習に楽しみを見つけていくことも良いのかなと思います。
実際「練習をこれだけしたよ」と目に見えるようにシール帳などを作ってみると、子供は喜んだりしていました。
毎日練習が基本とはいっても、体調が悪かったり、とてもハードなスケジュールの時は無理はしなくてもいいかと思います。
壁が出てきてうまく進めないときの対処法
毎日きちんと練習していても、必ず壁にはぶち当たります。
何回練習してもひっかかってばかりでうまく弾くことができず、悔しくて涙を流した記憶も私にはあります。
私の体験上、そういう時は、ひとまず、片手ずつゆっくり練習すると良いです。
右手だけをトコトン弾いてうまく弾けるようになったら、左手の練習というように、片手ずつ挑戦してみましょう。
片手ずつがうまく弾けるようになったところで、両手であわせて弾いてみます。最初はスローテンポでも大丈夫です。
だんだん慣れてくると、そのうち両手でスラスラと弾けるようになることが多かったです。
また、ひっかかりやすい所は、何回も同じ箇所を練習していきました。だんだんその前後の小節も交えて練習していきます。
何回も練習していくと、そのうち手が指の動きを覚えていくような感じがして、うまく弾けるようになりました。
あきらめないで、根気よくゆっくり挑戦していくことが、大事かなと思います。
壁を乗り越え、うまく弾けるようになった時の声かけ
3のように根気よく頑張っていくと、苦手な小節もだんだん上手に弾けるようになってきます。
「上手だね。」とただ褒めるだけでなく、どんなところが上手だったかなど、その子自身を認め、状況を受け止めてあげると次への自信につながるような気がしました。
「音の出し方に気持ちがこもっていて素敵だったね。」とか、「何回もあきらめずに弾いていたからカッコよかったな。」とか・・・。
とはいっても、私は忙しい時間に練習の感想を聞かれ、ついつい「上手。上手。」とサラッと言ってしまうことも多々あったのですが・・・。反省です。
きちんと聞いたり見たりする方も真剣さを求められますね。
まとめ
大事なのは、「楽しい」ということにつきるかもしれません。
楽しければ、練習も頑張れます。
親子で「楽しい」というココロを大切にすると、うまく進んでいくのかなと思いました。
今日も最後まで読んでくださりありがとうございました。


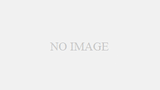

コメント